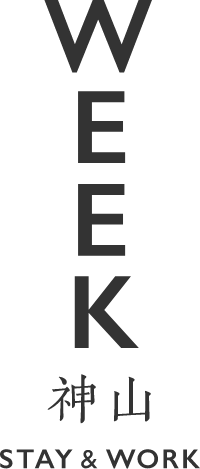勝浦川流域フィールド講座 レポート2
2025/09/17
こんにちは!WEEK神山いきもの担当の井上です。
今回は、勝浦川流域フィールド講座 レポート1に引き続き、勝浦川流域フィールド講座のレポートです。※第1回から第3回の報告もまとめているので、気になった方はぜひ読んでみてください)
第4回から第6回では、里山や人工林、農地における人といきものの関わりを観察してきました。
第4回 里山の魅力
樫原棚田周辺を訪れ、棚田周辺の里山やスギ林を見てきました。

里山は人が生きていくために管理してきた土地で、水田や畑、藪、雑木林など多様な環境がパッチ状に点在する環境です。これらの多様な環境があることで、それぞれに適応した昆虫や動物、植物が生息でき、生物多様性が高く維持されます。

「野となれ、山となれ」ということわざがありますが、日本の土地は放っておくと、農地⇨うっそうとした藪⇨地面まで日が当たらない極相林と移り変わっていくそうです。
全国の田舎から人が出ていき、管理放棄が進む今日の里山は多様な環境を失いかけています。日本のいきものの多くが姿を消し始めた要因の1つはここにあるのでしょう。

定期的な草刈りにより地面に光を届かせることで多くの野草が生えてきます。
オオバコは咳止め、ゲンノショウコは下痢止めや健胃など、身近な植物が薬や食料として活用されてきました。里山は現在のドラッグストアやコンビニの役割を果たしていたそうです。

次に人工林の中へ移動し、スギの本数や樹高を計測し、人工林の健康診断をしてきました。管理不足によりスギの密度が高すぎると細いスギが育ち、木材としての価値がなくなることに加え、樹冠が密となり地面に光が届かず林床の植物の数は減少します。木材資源になるようにと植えたスギですが、管理不足になると経済的にも環境的にもメリットの少ないものになってしまうそうです。

樹冠が開き、光が届くギャップ区で行った林床の植物調査では、14種の植物が観測されました。


中には、カンアオイやアオテンナンショウなどの希少な植物も見られました。
今後のスギ林の在り方を考えるうえで、スギを木材として活用することが難しいのであればパッチ上にスギの伐採を行い、伐採木は放置し、下層植生や陽樹林が育つ空間をつくることが必要なのかなと感じ、もっといろんな立場の人を交えて話してみたいと思いました。
第5回 里山で自然と生きる工夫
勝浦町坂本を訪れ、集落の暮らしや現状を見てきました。


昔と今の風景の違い。多くの山が農地として管理されていた様子が分かります。また、町を流れる勝浦川には船が通っていたそうです。

ここは、坂本に繋がるトンネル。馬車や人が行き交っていた様子が想像できました。
これらをみて、今では想像できないくらい多くの人が暮らしていたことが分かりました。

そんな坂本ですが、現在では多くの家や土地が藪に覆われつつあります。管理がされている家と空き家の見た目の差が大きかったです。日本の多くの田舎も同様の事象が起こっており、もっと時間がたてば山に飲まれ、遺跡になっていくのだろうなと感じました。

午後は、参加者の皆さんとお昼ご飯を作りました。講師の方々が道端からスベリヒユをとってきてくださり、おひたしにしたところ、触感は違いますがほうれん草と同じ味がしました。言われてみれば当たり前のことですが、里山は農地や資源、火を使えば、十分にご飯を食べていける場所だと気づきました。各資源について食べられるか否か、どうやって使うのかなどの知識を得ることが、里山を次世代に繋ぐポイントなのかもしれません。
第6回 里の暮らしと生きもの
徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の大原センター長にガイドをしてもらいながら、小松島市田浦地区を歩いてきました。ウメやサクラの樹木に集まるセミやカミキリムシの話、ミカンの木の新芽に産卵するアゲハチョウの話など身近にいるけど詳しく知らない昆虫の話にはワクワクが止まりませんでした。

用水路には、農地に水をくみ上げるための水車が回っていました。先人たちの知恵と木材と空き缶によって作られた水車は風情があり、かっこよかったです。ただ、耕作されなくなった農地も増えてきたらしく、この水車がある風景も失われていくような気がしました。

また、この用水路にはゲンジボタルが生息しているらしいです。ホタルが生息するには、餌のカワニナ、さなぎの際に利用する土手が必要とのことでした。コンクリート護岸された箇所は流れが速く、ホタルの生息には厳しいのではないかという疑問の声も聞こえてきました。
田浦地区のみなさんで年に数回、用水路の清掃を行うそうです。昔はビニールごみ等が捨てられていたそうですが、現在は水草が生え、アユやカマツカが泳ぐ美しい水路になっていました。

後半は、農薬の使用量を制限した米作りを行っている田んぼや脇の用水路でガサガサを行いました。

ガサガサの結果、メダカ、コシマゲンゴロウ、コオイムシ、マツモムシやガムシの仲間が見られ、水田を象徴するいきものたちがたくさん生息していました。中でも、子供(卵塊)を背負うことで知られるコオイムシは、個人的に徳島県で初めて観察することができテンションが上がりました。また、トリゲモの仲間など数を減らしている水草も見られました。
まとめ
第4-6回は、人の生活と自然環境の関係性について学ぶことができました。日本という土地では、ありのままの自然を残すことよりも、人の生活(農業や林業など)の中で自然を管理し続けていくことがいきもの保全には効果的であることを実際に目にすることができました。
多様な野草が生えるのは草刈りで開かれた土地、魚の重要な生息場所として機能するのは農業用水路、湿地を好む水生昆虫や水草が生息するのは水田、これらのように田舎ではごく当たり前にみられる環境を管理し、残していくことが理想ですね。
ただし、コンビニや百均ですべて手に入る豊かな日本において、自然資本視点での別の豊かさにどれだけの人が本気で向き合えるのかは正直わかりません。理想が理想で終わってしまう気もします。僕自身も現代の便利かつ簡単に手に入る豊かさから完全に抜け出すことはできないと思います。それでも、講師たちの自然資本を食料として、薬として、道具として認識している姿には、生きていくうえでの能力の高さがみられ、尊敬の念が生まれました。僕も利用できる自然資源の種類を増やしていきたいと思いました。
冷蔵庫に野菜がなければ、散歩や畑に出かけ、食べられる野草をとってきて食べるという選択肢のある町になると、持続可能な町として次世代に残っていくような気がしました。
また、佐那河内いきものふれあいの里の大原センター長をはじめ、講師や参加者の皆様と出会えることが本講座に参加するメリットだと思います。普段の生活では、なかなか出会うことが難しいはずのいきものに詳しい人と気軽に話せるのは、とても有意義な時間だと感じています。
ここでの出会いを見逃さず、定期的にコミュニケーションを取らせて頂き、神山町でいきものや自然資本についての取り組みを行う際に相談させていただける関係を築きたいです。先日は、大原センター長とかみかつ里山倶楽部の飯山さんに学生時代の研究内容を聞いてもらい、意見をいただきました。その後は、徳島や神山のいきものや自然についてフリートークをさせてただきました。研究室のような雰囲気が味わえました。
残りも少なくなってきた本講座ですが、次はどんないきもの有識者に出逢うことができるのか楽しみです。
- カテゴリー: